米国北西部の太平洋沿岸の海に潜ると、高い確率で幽霊のように白いイソギンチャクの森に遭遇する。ヒダベリイソギンチャクの仲間、ホワイトプラムドアネモネ(学名 Metridium farcimen)だ。
ホワイトプラムドアネモネは、高さが90センチにもなる世界最大級のイソギンチャクだが、何を食べているのかなど、生態についてはこれまでほとんど知られていなかった。
食べ物の特定が難しい理由は、ホワイトプラムドアネモネの触手が他のイソギンチャクと大きく異なっているためだ。イソギンチャクと言えば普通は、太くて長い触手を伸ばして獲物を捕らえ、毒を注入して動けなくする。だが、ホワイトプラムドアネモネの触手は細くて小さく、束のように密集している。「とても小さな生物を食べている証拠です」と、米ニューヨーク州立大学バッファロー校の海洋生態学者クリストファー・ウェルズ氏は言う。
獲物は、イソギンチャクの胃の中で消化されてドロドロに溶けるので、胃の内容物を顕微鏡で見ても、元の生物が何だったのかを判断するのは難しい。そこでウェルズ氏は、DNAバーコーディングと呼ばれる技術を使って胃の内容物を調べることにした。米国ワシントン州のフライデーハーバー港で捕らえた16匹のホワイトプラムドアネモネの胃の内容物を採取し、DNAの断片を分離して、既存のデータベースから一致する種を検索したのだ。
その結果、カイアシ類、フジツボ、カニの幼生など、予想通り小さな海洋生物のDNAが検出された。だが奇妙なことに陸生の昆虫のDNAも見つかった。ハエやハチなども見つかったが、最も多かったのはアリ。胃の内容物に含まれていた昆虫のDNAのうち98%が、Lasius pallitarsisというケアリのDNAで占められていた。(参考記事:「カニがイソギンチャクのクローン作り共生維持か」)
「とても驚きました。全く予想していませんでしたから」と、ウェルズ氏は言う。
イソギンチャクの胃の内容物を、初めてDNAメタバーコーディングを用いて調べたこの研究は、ウェルズ氏が筆頭著者となり、6月15日付で学術誌「Environmental DNA」に発表された。
からの記事と詳細 ( イソギンチャクがアリを食べると判明、予想外の結果 - ナショナル ジオグラフィック日本版 )
https://ift.tt/3hW5BWc

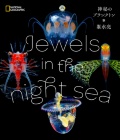
0 Comments:
Post a Comment